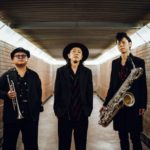力強いビートとガツンとしたアンサンブルで駆け抜けていく爆発力もこのバンドの強い魅力だけど、遠い空に瞬く星に願いを映すようなロマンを湛えた、繊細で儚い心の機微を捉えながらどこまでも大きな情景を描き出していく楽曲も、間違いなくハルカミライの真骨頂だ。中盤の“星世界航行曲”、“ウルトラマリン”、そして8ビートから8分の6拍子へと展開し、橋本が指揮者のように腕を振りながら大合唱を導いた“predawn”といった楽曲群では、そんなハルカミライという音楽の器の大きさと懐の深さが存分に発揮されていった。メンバー4人の声が重なるアカペラからのショートチューン“Tough to be a Hugh”2回まわしと、「俺の歌、めっちゃいいじゃん?――って言うと、おかんに『もっと謙虚になりなさい』と言われる」というエピソードを披露したMCを挟んでの、“21世紀”。暗転したステージに儚い光が降り注ぐ中、柔らかなファルセットを織り交ぜたミックスヴォイスの美しい歌唱を響かせながらスタートしたこの曲や、どっしりとしたミドルテンポで奏でる雄大なサウンドスケープの中でどデカい歌を響かせていく“ラブソング”の、まさにその歌詞通り愛も憎しみも、歓喜も悲哀も、そしてこの小さな生命の儚さも、そのすべてを包み込んでいくような親密でスケールの大きな歌に宿る、少しの驕りも偽りもない強さと美しさ。どちらもファーストミニアルバム『センスオブワンダー』に収録されている楽曲であり、つまりは最初期の頃から彼らの音楽には豊かな歌心が息づいていた証左でもあるわけだけど、長い月日の中でライブという表現と向かい合い、目の前のあなたと向かい合い、自分達の音楽と向かい合ってくる中で、その深みと説得力は確実に増した。

この2年半、コロナ禍以降のライブでは、冒頭にも書いた通り、彼らはそれまでの自分達のスタイルとは異なる形でハルカミライのライブを作り上げることを余儀なくされてきた。どういうことかと言うと、ダイブができない、すなわちテンションの高まりと共にメンバーが観客の中に突っ込んでいって歌ったり演奏したりという、かつてのハルカミライのライブではほぼ必ずと言っていいくらい目にしていた光景は禁じ手となり、彼らのライブにおけるエモーショナルな高揚感や一体感を形成するための大きな一端を担っていたオーディエンスとのシンガロングも、できない日々が続いた。特に彼らの場合は2020年の秋、ライブというものがようやくポツポツと再開され始めたばかりの最もルールが厳しい時期から率先してツアーを組み、全国のライブハウスを回り始めたわけだけど、当初はそれまでとはまったく異なる状況・雰囲気の中でのライブに戸惑い、メンバーいわく「全然ダメで、マジでクソみたいなライブして、食らいまくった」こともあったと話してくれたこともある。でも、そういう中でも自分達のライブを模索し、オーディエンスと共に熱狂の渦を生み出していくことでかけがえのない体験を作るのではなく、純粋に自分達の演奏で聴かせる/魅せることによって忘れられない体験を作り出すというライブに挑み続けたことによって、バンドはとても成長した。そもそもコロナ禍に突入するよりも前、フェスなどでもだんだんとステージが大きくなっていく中で、「ダイブに頼らずちゃんと伝わる曲を作ろう」というマインドから生まれたのが“PEAK’D YELLOW”だったりもするのだが、勢いだったり身体的なアクションに頼らずとも、その想いも衝動も、熱も激情もすべてをプレイに込め、歌に込め、しっかりと観客の心の奥深くに届けていくことに徹底して向かい合ってきたこの期間は、ライブバンドとしての彼らの地力と表現力にとても大きなものをもたらしたと思う。落ち着いたとか大人びたみたいなこととは違う。彼らは他の何でもなく、ただその「音楽」の中に、より自由に自分達を解放できるようになった。

序盤で演奏された“革命前夜”同様、初期デモ音源のみに収録されていた楽曲を昨年の10周年記念盤『Symbol 2』のタイミングで再録したうちの1曲でもある“city”から、ライブは徐々に終盤戦へと向かう――と言っても現場では、「あ、そろそろ終盤だな」などとは気づかなかったのだけど。時に心の深いところにタッチし、時にどこまでも飛んでいけそうな果てなき高揚を最大化し、そうやってそれぞれの楽曲が宿している豊かな緩急の中で感情を大きく揺り動かしながら、1曲ごとにハイライトとなる一瞬をひたすらに積み上げ続けていく。MCでは橋本の実家で親が寝静まる中メンバー全員で夜通し飲み、橋本の父ちゃんが作ったブランコに小松が全裸で乗った話を暴露して場を和ませたかと思えば、自分達が所属するTHE NINTH APOLLOとユニバーサルミュージックのEMIレコーズに対する感謝を述べ、バンドと事務所、バンドとレーベル、どっちが土台とかどっちが引っ張るとかではなく、これから先も一緒に徒党を組んで進んでいきたいんだという話をバシッとしたのも印象的だった。
橋本のアカペラ独唱から始まり、<音に乗って 光になって/影が出来ても 希望になって/抱えた膝を解く涙になって/世界を変えて/君の僕になって>という、まるで彼らと音楽、リスナーとハルカミライの関係性を表しているかのような一節が響く“世界を終わらせて”からの、この日一番の大合唱で<ただ僕は正体を確実を知りたいんだ>とここに集ったすべての人の魂の叫びが武道館に轟いた“PEAK’D YELLOW”。強くタイトに跳ねるビートが前へ前へと進み、バンド全体がさらなる熱を帯びていく。関がドラムに仰向けに乗り上げてギターを掻き鳴らした後、最後はリズムを観客の巨大なクラップに任せ、小松もステージ前まで出てきて4人が横一線に並んで肩を組んだ。そして、ライブハウスで出会い、4人でしか漕げない船を漕いでいく中で多くのあなたに出会い、その先にこの武道館があったということをギター1本で静かに歌い上げた後に、「これは俺達の日記みたいなもん」と、バンドの歩みの中でこの4人が育んできた関係性を歌った“赤青緑で白いうた”へ。そこに滲み出る想いが、ロックバンドという、単なる友人とも家族とも違う、儚いようでいて何より濃いものを分かち合い進んできた実感が、深くあたたかに聴き手の心をも満たしていく。

「せっかくだから」と観客を座らせ、夜空を見上げてあなたを想い、生きることを想う“宇宙飛行士”をしっとりと歌い上げ、“アストロビスタ”へ。曲間で「明日、ここでかまいたちのライブあるらしいよ。観てえよな。このままどっか隠れてようかな」なんてジョークを飛ばしてしんみりとした雰囲気に笑を差し込みつつ、<眠れない夜に俺たち ハルカミライを組んでさ/君の自慢のバンドに 少しずつ 俺達はなっていった>と歌詞を変えて歌った後、「そんな気がするんだよ。いつも最前を進めてたか、最善を選べてたかは全然わかんないけど、だけど進めてるし、これからも自信持ってやっていけそうです」と言った、その橋本の言葉は、ロックバンドをやる/ロックバンドを求める最も根源的かつ切なる衝動を歌い叫ぶこの曲と相まって、とても頼もしく響いた。
「誰かに半分渡したら、自分のものが半分になっちゃう。だけど一つだけ、誰かに渡しても半分にならないものがある。それは、今日みてえな幸せだよ」
幸せを、優しさを、愛を、今この同じ時を生きるあなたへと渡していくこと。その循環が、時に大げさじゃなく誰かの生命を救い、時に渡した側であるはずの自分自身をも救っていく。暗闇が完全に晴れることも、ひとり押し潰されそうな
不安や悲しみが消えることもないのかもしれないけれど、でもそうやって渡し続けていくことが、いつかどこかで、あるいは今この時、生きていくための大切な光となる。ハルカミライは別に聖人君子じゃないし、完璧な人間であるわけでもない。だけど彼らは、孤独も闇も痛みも苦しさも知っているからこそ、それでも光を諦めることなく追い求め続けているからこそ、そのことを真摯に、自分達に歌える言葉で、全力で音楽にしていく。だからハルカミライの歌は、綺麗事なんかじゃない、人生を支える歌となる。だからハルカミライのライブは、こんなにもあたたかくて、こんなにも美しい。
本編最後に奏でられたのは“ベターハーフ”、“パレード”、そして“To Bring BACK MEMORIES”。とても満ち足りた、それぞれがそれぞれに、だけど今日この場所・この体験をシェアしたからこそどこかで同じ時を生きる者の存在を感じながらまた明日を歩いていくことができる、そんなポジティヴなフィールが溢れた武道館。ラストは豪快なショートチューンをデッカく打ち上げてこの先を誓い、晴れやかにステージを去っていった。
アンコールもまた、実にハルカミライらしかった。観客からリクエストを募って(一斉に上がる声に、果たして本当に聞き取れたのかは不明だけど。笑)“THE BAND STAR”〜“君と僕にしか出来ない事がある”を奏で、間髪入れずに“春はあけぼの”へとなだれ込んでいく。メンバーも観客も本当に今この瞬間を心から楽しんでくることが、肌で伝わってくる。「これやっぱ、好きな曲やったほうがいいよな」という須藤の呟きに再びフロアからリクエスト曲がバンバン飛ぶが、「いや、好きな曲って、みんなのじゃなくて、俺達のね。みんなのは最初に聞いたでしょ」と言って“それいけステアーズ”へ。もちろん観客もワーッと歓声を上げ、みんなのシンガロングも巻き込みながら、幸福なヴァイブスがさらに天井知らずに湧き上がっていく。
「俺らに残された生命はあと20分。21時までに終わりです!みたいなアナウンスしないといけないらしくて……頑張る」と橋本が言い、須藤の「まず絶対にやりたい曲をやったほうがいいんじゃない?」という言葉で話し合って始まったのは、“Symbol 2”。昨年末にドロップした10周年記念EPの表題曲であり、これまで使ってこなかったピアノやティンパニなどの音も自分達でたくさん入れて自由に作り上げた楽曲。須藤がキーボードを担当し、揺蕩うように心地いい8分の6拍子のサウンドの上を、流線型のメロディが美しい軌道を描いて飛んでいく。
「今日はめでたいから“みどり”やって!」という観客の声に応えて“みどり”を演奏した後、最後の最後はやはりこの曲、“ヨーロービル、朝”。「俺達のこの先、11周年、13周年、ずっと先に向けて」という言葉と共に美しいアルペジオが放たれ、橋本の豊かな、あらゆる感情を受け止めて解き放っていくような大きな歌がどこまでも響いていく。しっかりとガッチリと噛み合いながら地を蹴って進むバンドサウンドが雄大な景色を描き出し、ハルカミライの初武道館は大団円を迎えた。デッカい「ありがとねー!」を残してメンバーがステージを後にして即、本当に即、終演のアナウンスが流れたのは20時58分。無事に持ち時間のすべてを使い切り、全力で魂を燃やし尽くし、幕を閉じた。
バンドは、その始まりはひとつの奇跡みたいなものだ。この4人が同じ時代に生まれ、出会い、共に音と鳴らすようになった、その奇跡。誰かひとりが欠けても決して同じにはならない、ロックバンドというものはどれだけ強く見えてもそれくらい繊細な生き物で、だからこそ面白い。
だけど同時に、バンドは、奇跡なんてものだけでは絶対に続かない。
そもそも異なる人間である4人がたったひとつの運命共同体として音楽を追い求め、生きていくこと。その道中では自分達の望まないことだって起こるし、上手くいかないことも、悔しい思いをすることもたくさんあるだろう。ちょっとしたボタンの掛け違えでも、その気持ちを放置してしまえば簡単に空中分解してしまうことだってある。この日、“赤青緑で白いうた”の曲中で、橋本は「凄いねって言われると、俺は運がよかっただけだよって答える。でも本当はそんなこと思ってない。運のおかげでも、神様のおかげでもない、俺達4人が辿り着いた今日だよ」と噛み締めるように言ったが、10年という決して短くない期間、お互いの人生を重ね合わせ、時にはあーだこーだ言い合ったり歯を食いしばったりしながら、笑って泣いてたくさんの経験を分かち合い、一つひとつ懸命に向かい合って乗り越えてきたからこそ、このバンドは続いてきた。そして、そうやって生きてきたバンドだからこそ歌える歌が、鳴らせる音が、今ここにある。
ハルカミライの今回の日本武道館ライブはまさしくそういうものだったし、きっとこれからもこのバンドはそうやって歩いていくのだということを確信させるに足るものだった。彼らのライブはいつだってそうで、それは小さいライブハウスであろうがどデカいアリーナであろうが変わらないのだけど、でもやっぱりちょっとだけ、この日の武道館ライブは特別だった。ここまでストラグルし続けてきたハルカミライの10年に対する確信と肯定と祝福が、この先の未来への灯火となって力強く輝いていた。
誰の人生においてもそうであるように、ハルカミライは答え無い答えを、その正体を、4人で追いかけ続ける。それが音楽となって私達の日々を照らし、今を越えて遙かなる未来へと向かう。そんなハルカミライの大切な礎が、この日、またひとつ増えた。それは本当に素晴らしい、一瞬にして永遠、だった。
有泉智子(MUSICA編集長)
【2023年2月1日(水)SET LIST】
1.君にしか
2.カントリーロード
3.ファイト!!
4.俺達が呼んでいる
5.フルアイビール
6.革命前夜
7.フュージョン
8.エース
9.QUATTRO YOUTH
10.春のテーマ
11.幸せになろうよ
12.星世界航空曲
13.ウルトラマリン
14.predawn
15.Tough to be a Hugh
16.Tough to be a Hugh
17.21世紀
18.Mayday
19.ラブソング
20.city
21.光インザファミリー
22.ピンクムーン
23.世界を終わらせて
24.PEAK’D YELLOW
25.赤青緑で白いうた
26.宇宙飛行士
27.アストロビスタ
28.ベターハーフ
29.パレード
30.To Bring BACK MEMORIES
[ENCORE]
31.THE BAND STAR
32.君と僕にしか出来ないことがある
33.春はあけぼの
34.それいけステアーズ
35.Symbol 2
36.みどり
37.ヨーロービル、朝
写真 Takeshi Yao / 小林歩
2