
—「LIMIT CODE」を作るにはこの3年が必要だった
─結成から1st LIVE「R2Y+J主催EVENT R2Y’s Park area 0.0〜破壊の迷宮〜」まで約4ヶ月、その僅かな期間にどのくらいの楽曲を生み出されたのですか?
A・O・I:6曲くらいですね。ただ、「LOST/SONIC WAVE/ANSWER」のときまでは、自分のギターとヴォーカルのダビング量も多かったり、現在のR2Y+Jスタイルに辿り着いていないんですよ。イベントやレコーディングを重ねる毎に音数が減ってきて、それによってスタジオでのセッションも充実して。まだまだ進化をしている最中だと思うんですが、要はライブで3ピースをやったことがなかったら、正解が良く解らなかったんです。自分のヴォーカルギターと言うスタイルをどうバンドに落とし込んでバランスを取るかに、いまいちしっくりとしていない部分もあったし。それがだんだん見えてきた結果、音数が減ってくる(笑)。
─単純に言うと、R2Y+Jとしてのスタイルに自信がついてきたんでしょうね。
A・O・I:そうですね。このバンドと自分のスタイルにね。あとは”スペイシーなものをやりたい”ということもずっと繋がっていて。それはギターの音作りが1番なんですけど、自分のギターの音色一発で、バンド全体をまとめられれば、リズム隊のベースとドラムにグルーヴを任せ、楽曲の持つ世界を表現できるというね。
─特に「CRAWLER/TWILIGHT/UNIVERSE」では、その要素が垣間見れています。
A・O・I:やっとそういう感じになりましたね。今回の「LIMIT CODE」で、更に4曲を録音したんですけど、それを上回るくらいダビングをしなかったんです。もしかしたらその反動で、次のレコーディングですごいダビングをするかもしれないですけど(笑)。
─“足りない”という観点からの足し算よりも、”要らない”という肯定的な引き算というのは、3ピースだからこそなのでしょうか?
A・O・I:昔もそうでしたけど、やっぱり最初は見えていない怖さから、どんどん音を詰め込んでいくんですよね。極端に減らしたとしても、最終的なマスタリングにならないと、まとまり方や聴き応えまでわからないですし。試しながらですけど、削ぎ落とすことが表現に繋がるように、形にしていきましたね。
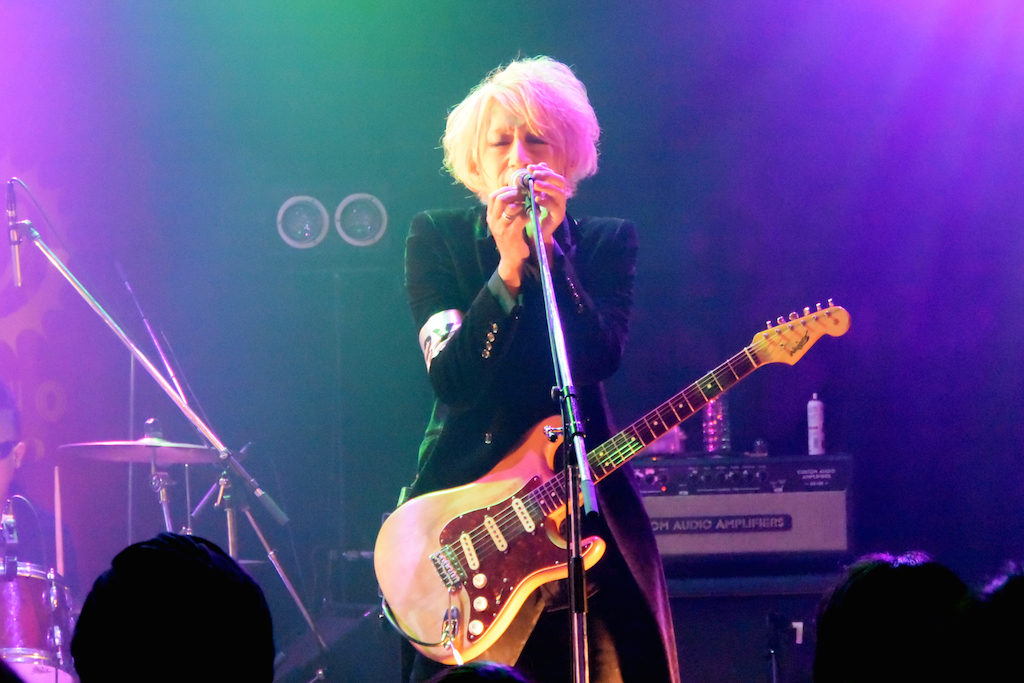
─A・O・Iさんは”怖い”という表現をされましたが、音の武装を取っ払うことで、ある意味、裸の勝負ができるということでもありますよね。
Lüna:最初の頃は、ライブでもマニピュレーターの人がいたりとか、途中でサポート・ギターを入れたりとかしていたんですけど、あるときから”3人でできるじゃん”っていう感じ。それはA・O・Iくんが言ったことが1番大きいんだけど、サポート・ギターをなくすことで空間ができるから、自由にリズム隊だけでグルーヴを出せるようになる。同期を効かしてたけど、今や残骸のように(笑)、殆ど残ってないんで。そこに辿り着くまでのライブであったし、音源の方でも同じようなラインで辿ってきて、それが今のR2Y+Jなんですよね。
─メインの活動がライブである以上、そこでの気づきが自ずとレコーディングでも反映されるでしょうし。
Lüna:そうなんですけど、初期の頃はそんなにライブをやらず、3ヶ月に1度の主催イベントをやるっていうペースを頑なに守っていて。それ以外のお誘いもいただいていたんですけど、全部お断りしていて。その代わり、その3ヶ月分を1本に凝縮することで、次の3ヶ月後まで充電もしつつ、楽曲にも凝縮していけてたと思うし。
─その頑なに自分たちのペースを保っていたのは、R2Y+Jとしてのブレない表現の土台は、そうまでしないと構築できなかったからでしょうか?
Lüna:ホントはね、初めの勢いをつけるためにもライブをやりたかった面もあるんですけど、ライブをこなしていくことを優先させてしまうと、表現の純度が薄れてしまっていた気もするし。そうではない、ガッツリ固めたものをコンセプトとして表現していくことは、ガマンも強いられましたけど(笑)、今となっては大きかったなと思いますね。A・O・Iくんも言っている通り、「CRAWLER/TWILIGHT/UNIVERSE」辺りからスタイルが確立されて、自分らでもその頑なに守ったペースを崩して、ライブの本数自体も増やしていきましたね。対外試合じゃないですけど、人のイベントに参加したりしても、自分たちを表現できるところまで行けた感じがあって。T-Tくんは、3ヶ月に1回のペースでも必死でしたけど(笑)。
T-T:やることが多かったんですよ(笑)。当時は同期モノを使っていたので、それ自体に慣れてもいなかった中で準備をしていたので、頭の中はいっぱいいっぱいでしたね。
A・O・I:拡声器にも色を塗ったりね(笑)。
T-T:(笑)。モチーフで拡声器を使っていたんですけど、ライブの前日に塗ったりとかもしてましたね。
A・O・I:美術だよね。
Lüna:3人で衣装を探しに行ったりとか、腕章を作ろうって生地を探してきたり。
A・O・I:その腕章、僕が作ったんですけど、今でも使ってますよ。
Lüna:土台作りには必要な時期ですね。そういうことも含めて「LIMIT CODE」を作るにはこの3年が必要だったんだろうなと。
─見る人からすれば「そこまでやるの?」っていうくらい、メンバーでの行動が実直ですけど(笑)。
Lüna:思いついたことは、限りなく実現しようって。
A・O・I:誰かが思いついたことは断れないっていうね(笑)。
T-T:アイディアは大体2人からなんですけど、「やって」って言われたら断れないじゃないですか(笑)。もちろん、そのアイディア自体は面白いし、やってみたいって思うから、僕も楽しんでやっていますけどね。

─R2Y+Jとして、その3年もの経験があった上で「LIMIT CODE」の完成となったわけですが、対外的に見られれば「やっとファースト・アルバムなの?」っていう見方もあったと思うんですよ。でも、このお話を伺うことで納得もあれば、その理由が浮き彫りにもなりました。
Lüna:そうかもしれないですね。例えばこれまでリリース的には3枚出してきましたけど、プロモーションを殆どしてこなくて。”SHAZANA”って言ったりとかね(笑)。そういうのよりも、自分らを固めておかないといけなかったし。それが今、どこへ出ても自信が持てているから、こうやって話ができていると思います。
─1曲目の「BELEAVE」に、そういった今のR2Y+Jが詰め込まれている気がしました。
A・O・I:今回のアルバムの中で「BELEAVE」がバンドの中でも新しい曲にあたるんですけど、スタジオで鳴らしたときに、すごく”香った”んですよね。「TWLIGHT」や「LOST」のような、ドレミの3コードでマイナー曲ってこれまでにもたくさんやってるし、「BELEAVE」のコードの展開も浮遊感のあるスタンダードな入り口ですけど、雰囲気があるというか。
─言ってしまえば、見たことがあるコード進行なんていくらでもあるわけですし、寧ろそれをR2Y+Jで試したときにどういう表現が成せるかの方が大事ですよね。
A・O・I:そうですね。単純な3コードの展開で一斉にやれば、すぐに出来上がるけど面白くないし。”もっと違うことができるんじゃないか”って、試したくもなるし、「BELEAVE」を提案したときも”これならLünaさん大丈夫だな”みたいな(笑)、そういう感覚がありましたね。ただ、そういった曲の方がまとまりづらい。逆にすぐに出来てしまう曲は、そこから一度壊す作業が入るので、それはそれで時間が掛かります。
─そうやって作り上げられた「BELEAVE」が、バンドとしても新しい曲であるとのことですが、アルバムのオープニングを担うことになったのは、ある種、R2Y+Jの現在進行形を入り口としたかったからですか?
Lüna:「BELEAVE」はね、A・O・Iくんが言う通り匂いもあって、今の自分ららしい曲だから、アルバムのオープニングかラストにしようって思ってて。曲順自体、すごく考えたし悩んだんですけど、「SONIC WAVE」で締めるとなった瞬間に、1曲目ではまりましたね。ライブでも、「BELEAVE」がオープニングのときとエンディングのときがあって、どっちも受け持ってくれる曲ではあるんですね。
A・O・I:Lünaさんが良く言うんですけど”「BELEAVE」はキャッチーな曲ではなくて重い曲だ”って。自分としては、キャッチーな曲だと思っていたんですけど、それをキャッチーか否かという議論がありまして(笑)。
Lüna:(笑)。なんかの取材のときにも「すごくキャッチーですよ」って言われたんですよ。「そうですか?」みたいな感じで、サウンドだけで見たら決して軽くないし、寧ろ重いと思っていたんです。僕らリズム隊って、結構好き勝手にやってるんですけど、そうすると変なマニアックな方向に行っちゃったりとか、とんでもない暗い曲ができたりとかするんです。
─良し悪しは別にして、自己完結の音楽というか。
Lüna:世の中には、ミュージシャンの自己満足だけの音楽というのもあって、それはそれで良いんですけど、僕らはそれをやりたいわけではないので。だからといって、ただわかりやすいことだけやりたいわけでもないし、すごく閃いたことをやりたいんです。そういう重い方向や複雑な方向に行ったりしたものに、A・O・Iくんのキャッチーな旋律で包んでくれることで、全曲が聴きやすくなって、触りのいい曲に仕上がる。でも、その土台の中の部分は、全然わかりやすくなかったりするんで、さっきの「LOST」とかも僕の中ではリズムとか普通ではないと思ってるし(笑)。
T-T:ひたすらタムまわしをしてますからね。
Lüna:僕らはキャッチーっていう言葉自体は嫌いじゃないし、そういうわかりやすいものとマニアックなもののバランスがすごく良いのが「BELEAVE」だと思います。好き勝手やっても、A・O・Iくんまとめてくれる信頼感があるし、実際の仕上がりを見てもそうですし。

A・O・I:「CRAWLER/TWILIGHT/UNIVERSE」を出したときに大阪・名古屋と短いツアーをやったんですけど、そのツアーの1曲目を担ってくれていましたし、曲の頑張りが大きかったですね。Lünaさんは「あんな重い曲で始まったら、アルバム全曲を聴いてくれないんじゃないか?」って言っていましたけど、ライブを観に来てくれる方たちから”「BELEAVE」はキャッチーだ”というの話も聞きつつ。その前までは、オープニングはマキシとは変えた「VIBES」が1曲目っていう大筋があったくらいなんですけどね。
─収録される楽曲が同じだとしても、アルバムの表情や聴き方がガラリとかわりそうですよね。そこで「BELEAVE」のキャッチーか否かについては、伺った通りですが、オープニングの必然性はあるように思えます。「VIBES」だったとしたら、疾走感からのイメージでアルバムを聴こうとしてしまいそうですし。
Lüna:そうですね。最初の「VIBES」は、サビがなくてただのイケイケで激しい感じだったんですけど、A・O・Iくんがサビを付けてくれて、一気に広がったんですよね。
A・O・I:1st LIVE「R2Y+J主催EVENT R2Y’s Park area 0.0〜破壊の迷宮〜」のときのオープニングで、インスト的なものが欲しいというところから始まったんですけど、Lünaさんのベースのリフから膨らませていって、そのときはゲスト・ヴォーカルが歌っていたんですけど、そこからでしたね。
─1曲1曲で聴いてしまうと、良い意味で表情がバラバラだから、ライブの構成を考える上で、楽曲の役割みたいなものが自ずと決まっていくのかなという気もするのですが。
Lüna:決まった役割もあるけど、あんまり決まり過ぎるとやるのがイヤになったりもするし(笑)。例えば、イベントのセットリストは毎回変えていましたし。ただ、ライブの1曲目は重要で、「BELEAVE」と決めたら、納得するまで暫くの間は変えないですね。それをやりつくしたら違う曲になるし、今は「VIBES」を1曲目にしていて極めようとしていますね。
A・O・I:そういう執着はありますね。ライブによって演奏時間も変わるので、Lünaさんが言ったように、出だしを極めるまで変えない分、あとの曲の構成にかなりの時間を費やしますね。
Lüna:だからライブ1本に対してのリハーサルも多いんですよ(笑)。個人的には、体にちゃんと入っていないと考えながらライブをしてしまうので、それを避けたいんですよね。細かい曲間のタイミングまでも含めて、無心とまでいかなくても体に入れておきたいんです。そこまでやると、新鮮じゃないって思う人もいるかもしれないですけど、僕は馴染まないとやれないので、みんなに付き合ってもらって(笑)。
A・O・I:僕もそっち派なんで (笑)。決めないでやるのも確かに楽しいですけど、R2Y+Jの現場はそうじゃないんです。同期もないですし、ライブで更なる表現をする為の”自由”で壊すには、最低限決めた土台が必要なんですよね。これまで色々と経験してきたからこそ、ある程度の自由度を削ぎ落としていた方が楽しめるし、本番中に自由なだけではダメというか物足りないということなんですよね。
─最初に3ヶ月に1回だけライブをやるということにも繋がっていますよね。
A・O・I:勢いだけでやると擦り切れることを知っていますからね。やることに意義があるというよりは、何をやるかの方が大事なんです。














