—Jさんの音楽への嗅覚と言ったら良いのか、日々アンテナを張ってないと当然ピックアップできないラインアップです。Jさん自身、常に分け隔てない刺激を求めた上での音楽の聴き方をずっとされているんですか?

J:そうね。俺ね、音楽好きは皆ジャーナリストだと思うんだ。みんなだって、新しいアーティストを探してるでしょ?「◯◯バンドの◯枚目のアルバムは最高だったよね、◯◯のライブは凄かったみたいだよ」って。それにロックミュージックは、どこの誰よりもジャーナリズムを持った人間たちが聴いてる音楽だと思うし、純粋にそれだけなんだよね。で、◯◯系の話もそうだけど、年齢や世代、もしかしたらデビューしてるしてないとかさえも、取っ払った所で俺は音楽を捉えてるんだよね。音楽って、俺はただの空気の揺れだと思うんだけど、それが「届くものと届かないものが何であるんだろう?その空気の揺れが、どうして人の心をこれだけ打つんだろう?」って常に思ってる人間だから。そういった意味では、アンテナを張るというよりも、いつもその熱に触れていたいという気持ちで、俺はバンド始める前からそこに居るんだよね。だから横への部分はとても自然なことだし、もしかしたら俺が一番興味があることって、この瞬間にも生まれているかもしれない、時代をひっくり返す様なとんでもない音に早く触れたいことなのかもしれないね。
—その空気には、五感を刺激するダイナミズムが存在していることへ気づくには、隔たりも色眼鏡も邪魔だと。
J:そう。それが存在だったり、もしかしたら言葉だったり、写真に写った被写体の目だったり、佇まいだったりするかもしれない。その全てに”ピーン”と引っかかる様なアーティストって、まだまだ沢山いると思うし。耳を澄ますというよりも心を澄まして、色眼鏡を自分で外せるような存在でいたいと思うしね。
—その色眼鏡が無かったとしても、単純に意外だったのが第1弾目の「ヒトリエ」。
J:彼らは、俺がやってるラジオ番組に来てもらったんですよ。そのときにアルバムを聴かせて貰ったら、とんでもなくカッコ良かった。彼らがどういう経歴を持ってて、彼らがどういう境遇でバンドを演っているのかは、一切インフォメーションがない中で、ライブを一緒に演りたいなと思ったんだ。
—一緒に演りたいと思った部分を敢えて言葉するなら、Jさんの中で引っかかったというか刺激になったところはなんでしょう?
J:アルバムを聴いて思ったのが、彼らが創り出す世界が物凄く完成度が高かった。で、そこにある、彼らの情熱というのは半端なものではないと思ったんだよね。でも世代なのかな、汗臭さを感じないというか(笑)。
—逆にリアリティありますよね(笑)。
J:そうなの。それは脅威に感じるし、だからこそ何かのキッカケで爆発しそうなさ。
—そうか、脅威。刺激にもなる反面、ある種ライバルにもなり得るという感覚が、すごい新鮮です。

J:あ、本当?でもね、俺らはライブハウスに出るしか無かったけど、自分の世界観を外に出すツールが今は違う訳でしょ?
—今の時代だからこその、一つの方法論ではありますよね。
J:俺らの時代って、リアクションがダイレクトだったじゃない?良いライブをすれば盛り上がったし、悪いライブをすれば…ねぇ(笑)。でも、彼らもインターネット上にアップしてもスルーされる可能性だってある訳だもんね。ある意味、そこにある希望や絶望というものを超えて出てきたことは、すごいことだよね。
—インターネットで”出す”というハードルは無いに等しいですが、”抜きに出る”というハードルで言えば、例えば鹿鳴館に出演するオーディションを突破することと同じかもしれないですね。
J:まぁ、あの時代のライブハウスって、ホント凄かったからね。でも音量で誤魔化せるってところもあるしね(笑)。でも今の時代の彼らはそのときに世界が完成していないといけないんだもんね。
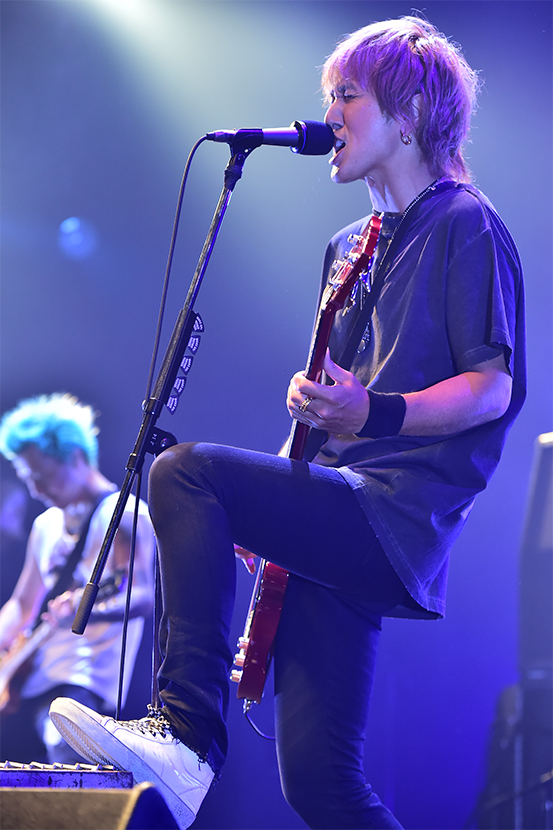
—先ほどの話じゃないですけど、それだけ今も個性を打ち出していくのは大変ですし、その個性が抜きに出たバンドだと思いますね。次の「The Cheserasera」は、3ピースのロックバンドで、メロディーがすごい特徴的です。
J:彼らも、ラジオにゲストに来てくれて初めて会ったんだけど、音を初めて聴いたとき、一聴すると爽やかな印象になるんだけど、それだけじゃなく肉体性がありパワーを感じる部分があって。彼ら必殺のフォーマットである「メロディーをちゃんと聴かせる」っていう曲の創り方もそうだし、彼らの「The Cheseraseraってバンドはこうだよ」っていう、1曲の中に詰め込む必殺の手法を既に持ってるバンドだなと思って。
—Jさんから比べると、年齢的には若いバンドではありますけど、The Cheseraseraとして完成しているものをちゃんと自分たちで理解して打ち出せていますよね。
J:そう、すごいよ。3分間の中でメロディー昇華の仕方、バンドとしての表現の仕方がこんなに美しくていいのかなって思うくらい、彼らなりの手法を持ってるバンドだなって。ホント、まさに必殺。そんなバンドと一緒にライブを演れたら面白いだろうと思って、今回は声を掛けさせてもらったんだ。
—世代的にも「Jさんと!?」という、恐縮とまでは言わないですけど、そういう感じはあると思いますよ。
J:みんなそう言うんだけどさ、ライブの本番になったら凄かったりするんだよね(笑)。
—(笑)。でも、Jさんはそれ分かってるから、こうやって声を掛けられるんですよね。
J:そうそう。音楽的に俺とは違うからこそ、余計ギャップっていうのが楽しめるものになると思うし。でも、「ヒトリエ」も「The Cheserasera」も”そこに流れてる熱さっていうものは一緒なんだよ”っていうのを見てもらえると思ったから、オープニングの2日間をお願いさせてもらったんだよ。
—最初の2日間から、前回「J AKASAKA BLITZ 5days -LIKE A FIRE WHIRL-」を超えるグレードアップだと思います。「Nothing’s Carved In Stone」は、ある意味Jさんらしいフックアップの仕方ですね。
J:ギターのウブ(生形 真一)君は、お互いに酒を飲まないんだけど、飲み仲間で(笑)。
—それどういう事ですか(笑)?
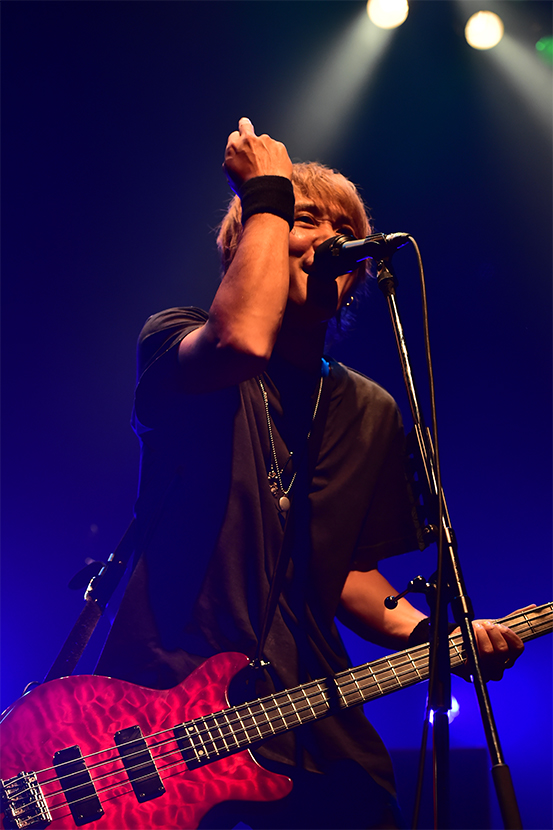
J:いや、みんなで飲んでる場所によく居るっていうか。ボーカルの(松村)拓もね(笑)。ウブ君は俺がやってるアコースティックプロジェクトの「Dessert Flame Frequency」にゲスト・ギタリストでプレイしてくれたり。「Nothing’s Carved In Stone」はロック・バンドとして地に足がついてるというか… もう外タレだよね(笑)。
—(笑)。でも、仰ることは良くわかります。
J:拓のボーカルの声なんてね、男が聴いてもカッコいい声だしさ、リズム隊もパーフェクトでしょ?
—このシリーズの渋谷TSUTAYA O-EASTの中で、かなりハードな夜になるんじゃないかと思いますし、良い意味で来る人も覚悟して来て欲しいですね。
J:結構楽しい夜になりそうだよ(笑)。
—そして次の「lynch.」は、満を持してという感じがしています。
J:「lynch.」とは初めて一緒に演るんだよ。もっと昔に「lynch.っていう、カッコいいバンドがいるんだよ」っていう紹介をしてもらってて、存在は知ってたし、ボーカルの葉月は地方のライブにも来てくれたりもしてて。色んな所で、俺のことやLUNA SEAのことをリスペクトしてるって言ってくれてるのも耳に入ってきてたしね。
—既にsold outもしていますし、チケットをゲットできた方は、是非楽しんでもらえたらと。
J:うん。みんなが期待してくれてたのが、やっぱりこういう部分でも形にになってると思うし、とんでもなく熱い夜になるね。俺も凄く楽しみにしてるんだ。
—次に、今回はこのシリーズで初にして唯一の大阪が選ばれ、相手が「KNOCK OUT MONKEY」。
J:ね。元々、俺のバンドでドラムを叩いてくれてるMASUOくんが「Jくん、カッコいいバンドいるんだよね」って、「KNOCK OUT MONKEY」のCDを持ってきてくれたのが最初だったんだ。聴かせてもらって、カッコいいと思ったし、ラジオで色々話したときも、エネルギッシュなメンバーだったし。このシリーズ化してるライブは、今まで東京でずっと演っていくのが多かったから、大阪まで巻き込んでやるには、大阪という地元の熱を知るバンドにオープニングゲストとして出てもらいたくて、「KNOCK OUT MONKEY」にお願いしたんだけどね。この間もhide兄のイベント(MIX LEMONeD JELLY)で久々に会って「よろしく!」なんて言ってたんだけど、せっかくのライブは観れなかったから。
—Jさんも、やっと大阪の地で観れるということで(笑)。そして東京に戻って「GOOD4NOTHING」。
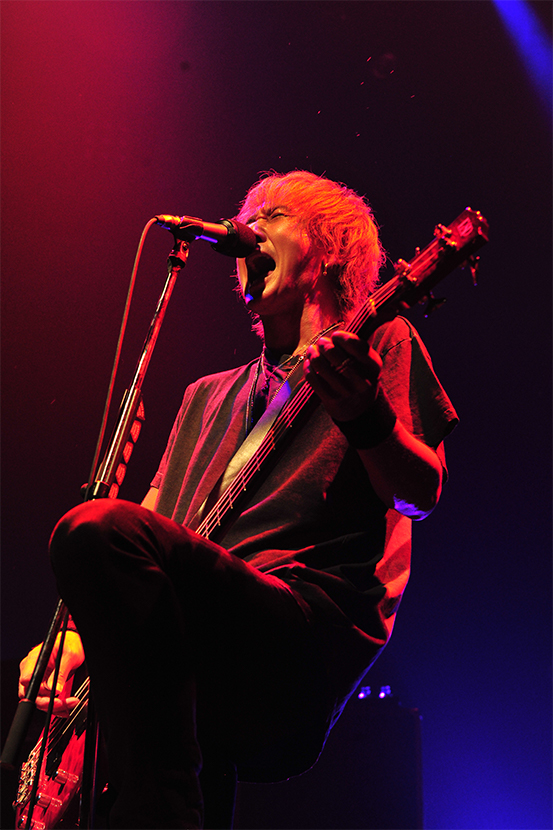
J:彼らもね、イベントとかで一緒に演らせて貰ったこともあったし。バンドとしてキャリアが長いバンドだから、当然存在も知ってて。やっと一緒に膝を突き合わせてライブが出来る(笑)。で、ギターのマサ(masasucks)がやっぱり彼らのことをリスペクトしてて、俺も今回こうやって一緒に出来るのはすごい嬉しい。
—今回のゲストアクトの選定にあたって、「ヒトリエ」や「The Cheserasera」のようにラジオからの入口が多かったように思うんですけれども、周りの身近なメンバーから入ってくる情報も、「GOOD4NOTHING」のように選定基準に入ってくるんですね。
J:もちろん。それはみんなの混じりっ気のない意見として取り入れるし、俺自身もカッコいいと思ったアーティストだからね。
—なるほど。実は「BACKLIFT」が結構意外でしいた。
J:そう?バンドをリサーチしてたときに彼らの存在というのを知って、実は今日もラジオで一緒だったんだよ。今回の彼らのシングルって、日本語で勝負してたりして最高なんだよ。でも、言葉を選ばずに言うんであれば、まさにこれからのバンドだと思うし、そのこれから何かを起こそうとしてる、熱を感じるバンドの一つなんだよね。だからこそ、その一つのきっかけとして、彼らにとってもとんでもない夜になれば良いなと思った。もっと言うとね、そういう意味で彼らが一番想像がつかない(笑)。
—(笑)。
J:でも、せっかくバンドであるわけじゃない?そこで何をやったって、このシーンに名前を残していくだけだからさ。それはどんな時代も変わらないことなんだよね。
—そうですね。このライブをきっかけに、脅威となって出てくるかもしれないですから。
J:そうそう。そういう未来っていうものを感じたバンドなんだよね。














